糖尿病・内分泌内科
2020年度 外来診療実績 : 4311名
| 外来診療実績 | 症例数 |
|---|---|
| 1型糖尿病 | 329 |
| 持続皮下インスリン注入療法使用 | 90 |
| 妊娠糖尿病や糖尿病合併妊娠 | 159 |
| 妊娠糖尿病 | 126 |
| 1型糖尿病合併妊娠 | 7 |
| 2型糖尿病合併妊娠 | 26 |
| 外来在宅療養指導(通算数) | 2651 |
| 糖尿病腎症透析予防指導 | 804 |
| フットケア | 799 |
| CSIIおよび持続血糖モニター指導 | 532 |
| 自己血糖測定導入指導 | 160 |
| 外来インスリン/GLP-1受容体作動薬自己注射導入 | 146 |
| その他 | 210 |
| 個人栄養指導(通算数) | 1702 |
2020年度 病棟入院実績 : 629症例
| 入院患者の原疾患による分類 | 症例数 |
|---|---|
| 1型糖尿病 | 41 |
| 2型糖尿病 | 527 |
| 妊娠糖尿病/糖尿病合併妊娠 | 28 |
| その他の糖尿病 | 26 |
| 低血糖の原因精査 | 4 |
| その他 | 3 |
| 入院目的による分類 | 症例数 |
|---|---|
| 血糖コントロール | 464 |
| 妊娠に関連した血糖管理 | 28 |
| 高血糖緊急症 | 11 |
| 低血糖症 | 6 |
| 合併症管理 | 29 |
| 血圧コントロール | 2 |
| 感染症 | 44 |
| 電解質異常 | 10 |
| 内分泌機能評価/治療 | 5 |
| 不明熱精査 | 5 |
| 循環器疾患 | 7 |
| 肝硬変 | 3 |
| その他 | 15 |
糖尿病内科医を目指す先生方へ
私たちは糖尿病内科医を目指す先生方を歓迎しています。
当科は数多くの糖尿病および合併症を扱っており、その症例数および種類の豊富さは大阪府でも有数の施設であり糖尿病専門医を目指すに不足ありません。
医学生、前期・後期臨床研修医、ならびに糖尿病専門医を目指す先生方へ、私たちは糖尿病専門医の育成に力を入れております。
病院見学や相談を随時受け付けています。下記アドレスまでご連絡ください。
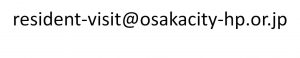
WEB予約はこちら
